瘀血の所見はさまざまであるが、その一つに臍もしくはその下の圧痛・硬結がある。平田道彦先生は、『痛みの漢方の実際』という本の中で、瘀血の所見として治打撲一方の腹部の圧痛点を挙げている。ツボで言えば肓兪あたりであろうか。
肓兪は当院の臨床で使うことが少ない経穴であるが、その古典の記載を見ると
- 心下大堅、大腹寒中、大便乾、腹中切痛。『明堂』
- 心下大堅、大腹寒中、大便乾、腹中切痛。『甲乙経』
- 大腹寒泄、大便乾燥、腹中切痛。『銅人』
- 腹痛寒泄、大便燥、目赤痛従内始。百証賦云、兼横骨、冝五淋之久積。『図翼』
などとある。肓兪は足少陰腎経であるとともに五臓六腑の海と言われる衝脈が通る経穴であるが、この所見から見れば寒邪や虚寒による気血の鬱滞を解除することができるのを読み取れる。下焦と中焦の鬱滞を解除して上下の交通を作るようなイメージであろうか。大便乾・大便燥などの文字も見えることから単なる寒邪や虚寒というよりは寒邪の凝滞性によって気機が通じなくなったものを通す作用が強いのかもしれない。




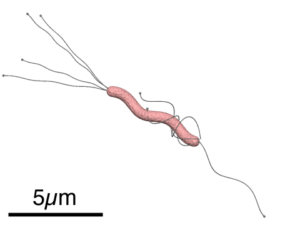

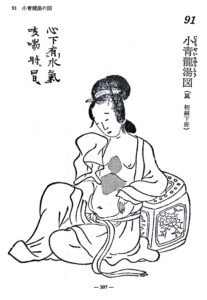
-300x300.jpg)
コメント