寒熱による鑑別は、鍼灸よりもむしろ湯液で重要視される。繰り返しにはなるが、李東垣は内傷を外感病に正気の虚が加わるもの・外傷を外感病があり正気が充実しているものとして考えている。
李東垣は内傷が頭痛・肩こり・腰痛などの点で外傷(太陽表証)と誤解しやすいと書いているが、現代ではむしろ内傷による頭痛や肩こりの方が多いであろうからこの辺りは時代背景を考えて読む必要があるだろう。いかんせん李東垣が生きていたこの時代は今より感染症が跋扈していたのは確実である。
翻訳文
外傷による寒邪の症状や、飲食の不摂生、過労による身体の損傷、また内傷に起因する飲食の問題はいずれも寒熱の弁別がある。世間では、内傷による飲食の不摂生や過労による不足の病を外傷の寒邪と表現して、表の実証と見誤って瀉してしまう。その結果、亡くなる者が多いことを私は言葉で言い尽くすことはできない。この(悲劇の)原因は、寒熱を区別しないことにある。そこで、これを細かく分けて解説する。
外傷による寒邪は、発熱と悪寒があり、寒熱が同時に現れる。発熱は翕翕(ジワジワ)と体温が上がるかと思えば、ふつふつと感覚を伴うもので、皮膚の表面に感じられる。この熱は表に存在するが、それは寒邪が表を侵し陽分を塞いでいるからである。その結果、陽気が発散できず発熱するのである。顔が赤く、鼻が詰まり、心煩が起こる。露出した肌が寒さに耐えられない状態(悪寒)であるが熱は皮膚表面に限られる。
悪寒はたとえ厚着をして暖炉の近くにいても寒さを防げない。一時的に寒さが増し、最終的には裏に伝わり裏証を引き起こして初めて治まる。寒熱が交互に生じることはなく連続して現れるのが特徴である。飲食の不摂生や過労による内傷にも、頭痛や肩こりや腰痛があり太陽表証と似ている部分はあるがそれ以外は異なる。これについては他の章で論じる。
原文
外傷寒邪之証、与飲食失節、労役形質之病、及内傷飲食、倶有寒熱。挙世尽将内傷飲食失節、労役不足之病、作外傷寒邪、表実有余之証、反泻其表、枉死者豈勝言哉!皆由不別其寒熱耳。今細為分解之。
『内外傷弁惑論』李東垣著
外傷寒邪、発熱悪寒、寒熱倶作。其熱也翕翕発熱、又為之払払発熱、発于皮毛之上、如羽毛之払、明其熱在表也、是寒邪犯高之高者也。皮膚毛竅者、陽之分也、是衛之元気所滋養之分也。以寒邪乗之、鬱遏陽分、陽不得伸、故発熱也。其面赤、鼻気壅塞不通、心中煩悶、稍似祖裸、露其皮膚、已不能禁其寒矣、其表上虚熱、止此而已。
其悪寒也、雖重衣下幕、逼近烈火、終不能禦其寒;一時一目、増加愈甚、必待伝入裏作下証乃罷。其寒熱倶作、無有間断也。其内傷飲食不節、或労役所傷、亦有頭痛、項痛、腰痛、与太陽表証微有相似、余皆不同、論中弁之矣




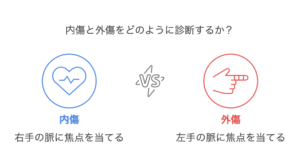


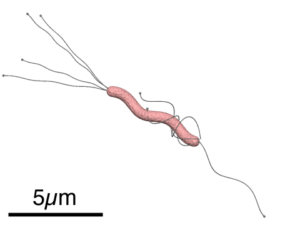
コメント