黎明期
慢性胃炎の黎明期
慢性胃炎は、古くは18世紀にドイツの医師シュタール(Stahl)が感染症の際に胃壁に炎症が見られることを指摘した記録が残っています。その後、フランスの軍医ブルサ(F. Broussais)によって胃炎(gastritides)という名前が付けられました。当時は、多くの従軍兵士にこの胃炎が認められていたため病気ではないと考えられていました。
しかし19世紀に入ると、組織学的な調査や胃カテーテルの使用などによって生きたままの胃を調べることが可能となります。これにより、胃炎が局所性なのかびまん性(全体性)なのか、単なる胃壁の炎症なのか潰瘍なのかなどがわかるようになりました。そしてイギリスの医師フェンウィック(Fenwick)が慢性胃炎は本質的に器質的疾患であるとの考えを示し、特に悪性貧血患者で見られる胃腺の萎縮性変化があることを報告しました。
20世紀に入ると、病理医のコンジェイ(Konjetzny)が胃癌や消化性潰瘍患者の切除胃を詳細に調べ、胃炎が存在すれば潰瘍や胃癌の土壌となりうる説を唱えます。これは現代でも「(胃壁の)萎縮→腸上皮化生→異形成→胃癌」の過程を辿ることが知られており、彼の臨床眼の鋭さを表すエピソードの一つでしょう。このようにして(慢性)胃炎は、診察技術の発展とともに病気として理解されてきました。
機能性ディスペプシアの黎明期
「ディスペプシア(dyspepsia)」とはギリシャ語で「消化不良」を意味する言葉で、古くから漠然と上腹部の不快症状全般を指す用語として用いられてきました。その後の19世紀には胃炎の発見に伴ってか「胃炎」という診断がしばしば「消化不良(ディスペプシア)」と同一視され用語の混乱が起こります。しかし、胃のX線撮影が可能となると胃潰瘍がないにも関わらず、潰瘍の所見がないにもかかわらず潰瘍様の症状を呈する患者群が認識され始めました。そこで米国の医師ウォルター・アルバレズ(Walter Alvarez)は、X線検査で潰瘍が確認できないにもかかわらず胃痛などの症状を訴える患者を「機能性ディスペプシア」と呼び、胃炎と区別するためにこの用語を医学界に紹介しました。その後、「神経性胃炎」や「神経性消化不良」「胃アトニー」「非潰瘍性ディスペプシア」などと呼ばれ、明らかな器質疾患がなくとも上腹部症状を呈する一群のことを機能性ディスペプシアと呼ぶようになりました。
診断と分類へ
慢性胃炎の診断と分類
20世紀に入ると診断器具の発展もあり、胃炎が「慢性・急性」、「表層性・萎縮性・肥厚性」などに分類できるようになります。これらはいずれも肉眼もしくは顕微鏡で胃壁に異常が認められたものを分類していました。1990年代になると、慢性胃炎の分類は国際的な統一へと向かいます。1990年の世界消化器学会議で提唱された「シドニー分類」は、胃炎を組織学的所見と内視鏡所見の両面から評価する世界初の国際的な包括的な枠組みでした。
その後、更新シドニーシステム (Updated Sydney System)が提唱されており、このシステムにより世界中で慢性胃炎の診断基準が標準化され、単に「炎症の有無」を見るだけでなく将来の胃癌リスク評価につながる胃粘膜の状態評価が可能となったのです。現在では京都分類という方法が提唱され、従来の知見の歴史的背景を踏まえ、H. pylori感染の診断とリスク評価に基づく胃炎のマネジメントが行われるようになっています。
機能性ディスペプシアの診断と分類
一方で、慢性胃炎よりもより機能的な症状である機能性ディスペプシアは、胃炎よりも病気への理解が遅かったと言えるでしょう。実際、日本での保険適応は2013年と比較的最近です。機能性ディスペプシア(FD)が独立した疾患カテゴリーとして確立できた背景には「症状はあるが器質的異常がない」という病態への理解が深まる必要がありました。しかし近代以降の医学の発展により、これらの症状が消化管機能の微妙な異常に起因する可能性が明らかになってきました。機能性ディスペプシア(functional dyspepsia)という名称自体が解剖学的異常ではなく機能的な障害を強調することからもこのことがわかります。現在では、機能性ディスペプシアは機能性胃腸障害(Functional GI Disorder)に分類され、過敏性腸症候群(IBS)などと同様に脳-腸相互作用の失調によって生じる疾患と考えられています。
FDの病態生理に関する理解も、ここ数十年で大きく進展しました。従来は漠然とストレス・胃酸過多が原因などと考えられていましたが現在では多因子的なモデルが提唱されています。具体的には、胃・十二指腸の運動機能異常、内臓知覚過敏、幽門前庭部や小腸の軽度炎症、粘膜の免疫応答異常、腸内細菌叢の乱れ、中枢神経と自律神経系の調節異常などがFD発症に関わるとされています。これらは機能性ディスペプシアが、胃炎と違って単一の原因で説明できる疾患ではなく、症状主体の症候群(syndrome)であることを物語っています。
機能性ディスペプシアは大きく二つに分類されます。一つは食後のもたれ感や早期満腹感を主とする「食後愁訴症候群 (PDS)」と、もう一つは空腹時あるいは随時の心窩部痛・灼熱感を主とする「心窩部痛症候群 (EPS)」です。これらは患者の症状に応じて診断するよう提案されています。現在ではローマ基準(Rome IV)という国際的な評価方法があり、これによって病態が分類・把握されています。
機能性ディスペプシアと慢性胃炎の違い
このような経緯から現代の臨床において機能性ディスペプシア(FD)と慢性胃炎は明確に区別される概念です。しかし歴史的には両者の境界はあいまいで、特にFD概念が浸透する以前は、器質的異常のない上腹部症状にも「慢性胃炎」や「神経性胃炎」といった誤解をされることが少なくありませんでした。日本でもFDが保険病名となる2013年以前は、内視鏡検査で大きな異常がなくとも症状があれば便宜的に「慢性胃炎」と診断する慣習があったとされています。これは裏を返せばFD患者の多くが長年「胃炎」として扱われ、本当の病態に即したケアがなされて可能性が高いです。
機能性ディスペプシア(FD)と慢性胃炎は、一見すると共に上腹部の消化不良症状を呈する点で紛らわしいものの、その本質は大きく異なります。機能性ディスペプシアは症状の集合体として定義される機能異常であり、慢性胃炎も胃粘膜の慢性的炎症という形態学的実体によるものです。機能性ディスペプシアという概念の登場により、従来では慢性胃炎とひとくくりにされていた非器質性の上腹部症状に光が当てられ、患者の訴えがより適切に評価・対応されるようになってきています。
鍼灸治療も機能性ディスペプシアの選択肢に
機能性ディスペプシアと慢性胃炎は診断面のみならず、治療面でも炎症が原因の痛みである慢性胃炎は原因治療で治るが、FDの痛みは器質的原因がないため薬物治療だけでは根治が難しいという違いが存在します。当院では、これを鍼灸治療の面からサポートできないかと取り組んでいます。お困りの方は是非一度ご相談ください。



-211x300.jpg)
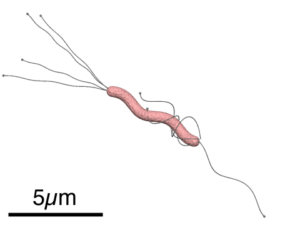



コメント